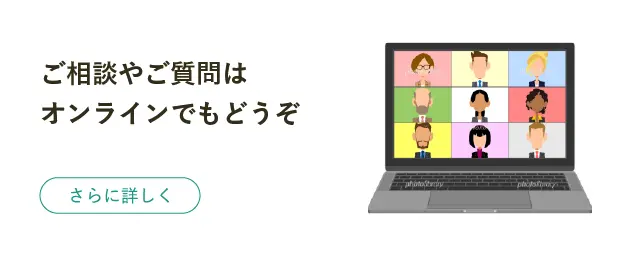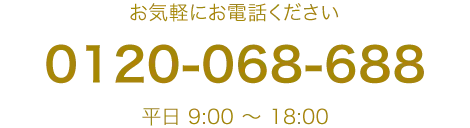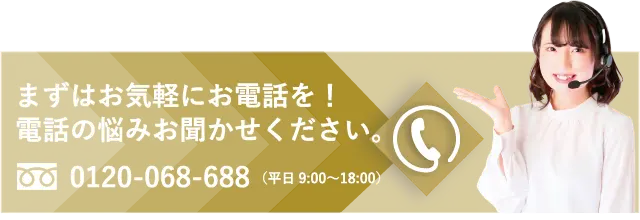電話代行の必要性
BCP対策とは?重要性や策定方法、業界別事例をわかりやすく解説!

地震や台風などの自然災害、サイバー攻撃、感染症の流行など、企業を取り巻くリスクは年々増加し、事業の継続が脅かされる場面が増えています。
「万が一、事業が停止したらどうなるのか?」
「取引先や顧客との信頼は維持できるのか?」
「従業員の安全や雇用をどう守るべきか?」
このような不安を抱えながらも、何から始めればよいかわからない企業も少なくありません。
そこで重要になるのが「BCP(事業継続計画)対策」です。
適切なBCP対策を講じることで、緊急時でも迅速に対応・復旧ができ、事業停止による損害や信頼の低下を最小限に抑えることが可能になります。
BCPは大企業だけのものではなく、中小企業や個人事業主にとっても経営戦略の一環として不可欠な取り組みです。
本記事では、「BCP対策とは何か」という基本から、具体的な策定方法、業界別の事例までを詳しく解説します。
また、「BCPとBCMの違い」「BCPと防災の違い」といった混同されやすいポイントも整理し、実践的なBCP導入のステップも紹介します。
目次
- 1. BCP対策とは
- 1-1.BCPとBCMの違い
- 1-2.BCPと防災の違い
- 2. BCP対策が必要な3つの理由
- 2-1.事業停止による損失を防ぐ
- 2-2.顧客・取引先の信頼を守る
- 2-3.従業員の安全と雇用を守る
- 3. BCPを策定する3つのメリット
- 3-1.競争力の強化と市場優位性の確保
- 3-2.法令・規制対応の強化
- 3-3.自社の強みと弱みを可視化できる
- 4. BCPの策定方法
- 4-1.事業影響分析(BIA)の実施
- 4-2.リスク評価と対策の策定
- 4-3.事業継続計画(BCP)の文書化
- 4-4.訓練とシミュレーションの実施
- 4-5.BCPの継続的な見直しと改善
- 5. BCP策定時に注意すべきポイント
- 5-1.定期的な見直しと更新を行う
- 5-2.実現可能な計画を策定する
- 5-3.訓練やシミュレーションを実施する
- 6. BCP対策における電話対応の重要性
- 6-1.緊急時の情報伝達手段としての電話の役割
- 6-2.コールセンター・電話代行サービスの活用
- 6-3.緊急時の電話対応マニュアルを策定する
- 7. まとめ
1.BCP対策とは
BCP対策とは、緊急時でも事業を継続または早期に復旧させるため、平常時から備えておく取り組みを指します。
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、企業が自然災害やサイバー攻撃、感染症の流行など緊急事態に備え、事業の継続や早期復旧を可能にするための計画です。
BCP対策を適切に講じることで、企業はリスクが発生しても迅速に復旧し、売上損失の回避、取引先との信用維持、従業員の安全確保が可能になります。
近年、日本では地震や台風などの自然災害の増加に加え、サイバー攻撃や感染症流行の脅威も拡大しており、BCP対策の必要性は今後さらに高まっていくでしょう。
特に、サプライチェーンの断絶やIT障害による影響は深刻で、業種を問わず、事業継続への備えが急務となっています。
1-1.BCPとBCMの違い
BCP(事業継続計画)とBCM(事業継続マネジメント)は混同されがちですが、それぞれ異なる役割と目的を持つ概念です。
BCPは「計画」に焦点を当てたものです。企業が緊急事態に備え、事業を継続または早期に復旧させるための具体的な対応計画を指します。
一方で、BCMはBCPを策定・管理・運用し、継続的に改善するための包括的な仕組みやプロセス全体のことです。
| 区分 | BCP(Business Continuity Plan) | BCM(Business Continuity Management) |
| 定義 | 企業が緊急事態において事業を継続・早期復旧するための計画 | 事業継続のための計画(BCP)を策定し、実施・管理・改善するためのプロセス全体 |
| 目的 | 事業の継続性を確保し、損害を最小限に抑える | 事業継続を確実にするため、BCPの適切な運用と見直しを行う |
| 実施範囲 | 災害発生時の具体的な対応計画 | 計画の策定、実施、訓練、評価、改善のサイクル全体 |
BCPを作るだけでは企業の事業継続は十分に担保されません。
BCPを実効性のあるものとして機能させるには、BCMの考えに基づいた継続的な見直しと改善が不可欠です。
企業は、定期的な訓練・評価・更新を通じて、BCPを実効性のあるものに改善し続けることが求められます。
1-2.BCPと防災の違い
BCPと防災も混同されがちですが、目的や対策内容には明確な違いがあります。
| 区分 | BCP(Business Continuity Plan) | 防災 |
| 定義 | 企業が事業を継続するための計画 | 災害そのものによる被害を防ぐための対策 |
| 目的 | 緊急事態発生時に事業を継続または早期復旧する | 人命や資産を守り、被害を最小限に抑える |
| 主な対策 | 代替拠点の確保、ITシステムのバックアップ、サプライチェーン対策 | 耐震補強、避難計画、火災防止、備蓄品の準備 |
| 実施範囲 | 企業活動全体の継続 | 企業活動全体の継続 |
BCPは事業の存続と回復に焦点を当てた計画です。
一方、防災は災害による直接的な被害を軽減することを目的としています。
どちらも企業にとって欠かせない備えですが、BCPは企業活動そのものを止めないための戦略であり、経営そのものの持続可能性に関わる取り組みです。
このように、BCP対策は企業の持続的な成長やリスク管理において欠かせない要素です。
次の章では、BCP対策が必要とされる理由や導入することで得られるメリット、そして具体的な策定方法について詳しく解説していきます。
2.BCP対策が必要な3つの理由
企業がBCP(事業継続計画)を策定し、適切な対策を講じることは、事業の継続を支えるだけでなく、顧客や取引先の信頼を守り、従業員の安全を確保する上でも極めて重要です。
本章では、BCP対策がなぜ必要とされるのか、その主な理由を3つに絞ってわかりやすく解説します。
2-1.事業停止による損失を防ぐ
自然災害やサイバー攻撃、設備の故障などが発生すると、企業の業務が停止し、売上の減少や取引先からの信用低下といった深刻な影響が生じます。
特に日本は、地震や台風などの自然災害が多く、BCP対策がなければ長期間にわたる事業停止を招く可能性があります。
BCP対策を実施すれば、緊急時にも代替手段を確保しやすくなり、損害を最小限に抑えることが可能です。
たとえば、クラウドを活用したリモートワーク環境の整備や、サーバーのバックアップ体制の強化によって、業務の早期再開を実現できます。
2-2.顧客・取引先の信頼を守る
企業が緊急時に対応できなければ、顧客は競合他社へ流れる可能性が高くなるでしょう。
また、取引先との契約履行が困難になれば、信用を失い、長期的な関係が破綻するリスクもあります。
近年は、ランサムウェア攻撃や情報漏洩の増加により、ITシステムの停止がそのまま業務停止に直結する企業も少なくありません。
特に金融機関やECサイトでは、わずかなシステム障害が信頼の喪失を招き、市場での競争力低下につながるおそれがあります。
こうした状況に備えるには、BCP対策の実施が不可欠です。
計画を事前に整えておくことで、緊急時にも迅速かつ適切な対応が可能となり、企業の信頼性を保つことができます。
たとえば、災害時の対応フローを明確にし、従業員への定期的な研修を実施しておくことで、対応の質とスピードを向上させることが可能です。
2-3.従業員の安全と雇用を守る
企業が災害やトラブル時に適切な対応を取れなければ、従業員の安全が脅かされるだけでなく、雇用の維持も困難になります。
2011年の東日本大震災では、復旧が遅れた企業が事業の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇に至った事例もありました。
こうした教訓を活かすためにも、BCP対策は事前に整えておくべきでしょう。
たとえば、リモートワークの導入や、非常時の連絡手段を整備することにより、従業員が混乱せず対応できる環境を築けます。
BCP対策は単なるリスク管理ではありません。
企業の持続的な成長と社会的責任の実現につながる重要な取り組みです。
3.BCPを策定する3つのメリット
企業がBCP(事業継続計画)を策定することには、多くのメリットがあります。
それは単なるリスク管理にとどまらず、競争力の向上や、法令遵守の強化など、経営全体に価値をもたらす取り組みです。
さらに、BCPの策定を通じて自社の強みと弱点を可視化できるため、今後の経営戦略にも活用できます。
3-1.競争力の強化と市場優位性の確保
BCPを策定しておくことで、緊急時にも迅速に対応できる体制が整い、市場での競争力向上につながります。
災害やトラブルが発生すると、多くの企業が業務を停止せざるを得ない場面に直面するでしょう。
しかし、BCPが適切に機能していれば、自社の事業を継続できる可能性が高まり、顧客や取引先からの信頼も保ちやすくなります。
たとえば、大規模災害時に同業他社が業務停止を余儀なくされる中でも、BCPを整えている企業は復旧が早く、顧客の期待に応えられます。
結果として、市場シェアの拡大という形で競争優位につながるのです。
さらに、リスク管理が徹底された企業は、投資家や取引先からの評価が高まり、新たなビジネスチャンスを得やすくなります。
3-2.法令・規制対応の強化
BCPの策定は、法令や業界ガイドラインへの対応を強化し、コンプライアンスの確保にもつながります。
特に金融機関、医療機関、インフラ関連の企業では、BCP対策の義務化や推奨が進行中です。
たとえば、医療機関では災害拠点病院におけるBCP策定が義務化されており、その他の病院でも策定が強く推奨されています。
また、介護業界では2024年4月からBCPの策定が義務化されるなど、各分野で対応が求められています。
さらに、国際的認証であるISO 22301(事業継続マネジメントシステム)を取得すれば、企業の信頼性が向上し、海外との取引や大手企業との契約でも優位に立てるでしょう。
BCPを導入することにより、法的リスクの回避と社会的信用の向上の両立が期待できます。
3-3.自社の強みと弱みを可視化できる
BCPの策定を通じて、自社の業務体制やリスクに対する脆弱性を明確にし、強み・弱みを客観的に把握できるようになります。
策定する過程では、企業は事業影響分析(BIA)を行い、自社の中核業務や必要なリソースを明確にする必要があります。
このプロセスを通じて、どのリスクに対して脆弱かを特定し、業務フローの課題や組織の強み・弱点を把握することが可能です。
たとえば、IT企業であればサーバーダウンやサイバー攻撃による業務停止リスクを分析し、適切な対策を講じる体制を整えることができます。
製造業では、サプライチェーンの脆弱性を洗い出し、代替供給ルートを確保することで、リスクを分散できるでしょう。
また、BCPの策定により、RTO(復旧時間目標)を設定することで、企業の復旧力を数値として把握できる点も大きなメリットです。
このように、企業の対応能力や柔軟性を定量的に評価することで、将来的な事業戦略の精度も高めることにもつながります。
4.BCPの策定方法
BCPの策定は、事業継続を確保するための重要なプロセスです。
計画的に進めることで、緊急時にも迅速かつ的確な対応が可能となります。
ここでは、BCPを策定するための基本的な手順を段階ごとに解説します。
4-1.事業影響分析(BIA)の実施
BCP策定の第一歩は、事業影響分析(BIA: Business Impact Analysis)の実施です。
これは、自社の業務プロセスが停止した際にどのような影響が生じるかを評価し、どの業務が事業継続にとって最も重要かを明らかにするプロセスです。
具体的には、以下のポイントを分析します。
・主要業務の特定と優先順位付け
・各業務の停止がもたらす財務的・運営的影響
・業務停止の許容時間(RTO: 復旧時間目標)の設定
BIAを行うことで、緊急時に優先的に復旧すべき業務を明確にできます。
4-2.リスク評価と対策の策定
次に、企業が直面しうるリスクを特定し、それに対する適切な対策を検討します。
想定されるリスクは、以下の通りです。
・自然災害(地震、台風、洪水など)
・サイバー攻撃や情報漏洩
・サプライチェーンの断絶
・停電や通信障害
それぞれのリスクについて、影響を最小限に抑えるための対策を立てることが重要です。
4-3.事業継続計画(BCP)の文書化
リスク評価を終えたら、BCPを正式な文書として整備します。
この文書には、以下のような要素を含めましょう。
・事業継続の目的と方針
・緊急時の対応手順
・代替手段や復旧手順
・役割分担と責任者の明確化
文書化しておくことで、従業員が緊急時に迷わず行動できるようになります。
4-4.訓練とシミュレーションの実施
計画を策定しただけでは十分とは言えません。従業員が実際に対応できるかを確認するため、定期的に訓練を実施しましょう。
主な訓練の種類は以下の通りです。
・デスクトップ演習(シナリオに基づく模擬訓練)
・実践的な避難訓練
・システム復旧訓練
訓練を通じて、BCPに実効性を検証し、必要に応じて計画を改善します。
4-5.BCPの継続的な見直しと改善
BCPは一度作成すれば終わりではありません。企業を取り巻く環境やリスクは常に変化するため、定期的な見直しと更新が不可欠です。
以下のようなタイミングでBCPの見直しを検討しましょう。
・新たなリスクの発生(新型ウイルスの流行、地政学的リスクの増大など)
・事業拠点やシステムの変更
・関連する法規制の改正
定期的な見直しと改善により、常に最新の状況に適応したBCPを維持できます。
5.BCP策定時に注意すべきポイント
BCP(事業継続計画)の策定では、単に計画を立てるだけでなく、実際に機能するかどうかを検証することが重要です。
緊急時に的確な対応ができるよう、計画の見直しや訓練の実施を通じて、現実的かつ継続的に運用できる体制を整える必要があります。
本章では、BCP策定時に特に注意したい3つのポイントについて解説します。
5-1.定期的な見直しと更新を行う
BCPは一度策定すれば終わりではありません。
変化する事業環境や社会情勢に応じて、継続的な見直しと更新が必要です。
リスク要因も年々異なり、新型コロナウイルスのようなパンデミックやサイバー攻撃の高度化など、予測が難しい事象が増えています。
そのため、少なくとも年に一度はBCPの内容を精査し、新たなリスクへの対応を反映させましょう。
また、有事の際、計画が実際に機能するかを検証するため、過去の対応実績や他社の事例も積極的に参考にすることが重要です。
■定期的な見直しのポイント
・法規制の変化:関連する法律やガイドラインの変更に対応する。
・業務プロセスの変更:事業拡大やシステム変更などに合わせてBCPを更新。
・新たなリスクの発生:災害の激甚化や攻撃手法の変化に備える。
・過去の対応事例の活用:実際の緊急事態から得た教訓を反映する。
5-2.実現可能な計画を策定する
BCPは、現実的に実行可能なものでなければ意味がありません。
いくら理想的な計画を立てても、リソースが不足していたり運用が複雑すぎたりすれば、緊急時に機能しないリスクが高まります。
そのため、企業の規模や業種に応じて、実現可能なBCPを構築することが求められるのです。
■実現可能なBCPを策定するためのポイント
・リソースの明確化:人員・予算・設備など、実際に使える資源を前提とする。
・簡潔で理解しやすい内容:全従業員がすぐに理解・行動できる計画にする。
・代替策の準備:外部委託先の確保やクラウドの活用など柔軟な選択肢を用意。
・関係者の役割を明確化:緊急時に「誰が何をすべきか」を具体的に定める。
たとえば、IT企業はデータバックアップやクラウド活用、製造業ではサプライチェーンの多重化を検討するなど、業界特性に応じた現実的な対策が求められます。
5-3.訓練やシミュレーションを実施する
計画を策定しただけでは、緊急時に十分な対応ができるとは限りません。
従業員が実際に行動できるかを確かめるためには、訓練やシミュレーションの実施が不可欠です。
■訓練の種類
・机上訓練(テーブルトップ演習):想定シナリオをもとに対応策を議論する。
・実動訓練:避難やシステム障害対応など、実際に動く訓練を行う。
・サプライチェーンのテスト:取引先・ベンダーとの連携体制を確認。
・サイバー攻撃対応訓練:ランサムウェアやDDoS攻撃を想定して実施。
訓練後は実施結果を記録し、課題を抽出して計画に反映させることが重要です。
シミュレーションによって浮かび上がる“想定外”の問題を可視化することで、BCPはより実践的なものへと進化します。
■訓練の実施ポイント
・現実的なケースを想定:自然災害、サイバー攻撃、パンデミックなどを基にシナリオを構築。
・全社的に参加できる形式を検討:管理職に限らず、一般社員も巻き込む。
・実施後の振り返りを徹底する:課題を洗い出し、次回の改善につなげる。
BCP対策は、策定して終わりではありません。運用と改善を繰り返すことで、企業の持続可能性と危機対応力は大きく向上します。
定期的な見直し、現実的な計画づくり、そして訓練の徹底を通じて、万が一の事態にも柔軟に対応できる体制を築いていきましょう。
6.BCP対策における電話対応の重要性
企業がBCP(事業継続計画)を策定する際、災害や緊急時のコミュニケーション手段の確保は最優先事項の一つに挙げられます。
なかでも「電話」は、従業員・取引先・顧客と連絡を取るための即時性と確実性を備えた手段として、非常に重要な役割です。
もし電話対応の整備が不十分であれば、情報伝達の遅れから混乱が生じ、迅速な意思決定が困難となる恐れがあります。
その結果、事業の中断が長期化し、信用の失墜や売上損失につながる可能性も否定できません。
BCP対策において、電話はしばしば 「最後の頼みの綱」 となります。
災害時やシステム障害時でも、安定して利用できる通信手段として機能し続ける強みがあるのです。
あらかじめ電話対応体制を整備しておくことで、顧客や取引先の信頼を維持し、事業継続の可能性を高めることができます。
そのためには、以下のような事前準備が不可欠です。
・コールセンターや電話代行サービスの活用
・PBX(構内交換機)の設定やクラウド化
・緊急時の電話対応マニュアルの策定
これらを備えておけば、どのような状況下でも 適切な電話対応が可能となり、企業の危機管理能力が格段に向上します。
6-1.緊急時の情報伝達手段としての電話の役割
災害、サイバー攻撃、通信障害などが発生すると、Webサイトやメールといったオンライン手段が使用不能になるケースがあります。
特に大規模災害時には、インターネット回線そのものが不安定になり、情報発信が困難になることも少なくありません。
こうした状況でも、電話は比較的安定して利用できる手段として有効です。
非常時における情報伝達の確保には、電話体制の整備が欠かせません。
6-2.コールセンター・電話代行サービスの活用
災害や緊急時には、自社での電話対応が難しくなる状況も想定されます。
オフィスが被災した場合や、従業員が出社できない場合には、電話対応の負荷が一気に高まるため、業務の継続が困難になる恐れがあります。
このような事態に備えて、コールセンターや電話代行サービスを活用することは非常に有効です。
■電話代行サービスの主なメリット
・拠点が被災しても、外部のサービスによる対応が可能
・営業時間外や混雑時でも、柔軟な電話対応が実現できる
・取引先や顧客へ安心感を与え、企業の信頼維持に貢献する
特に、 クラウドPBXを導入すれば、リモート環境下でもスムーズな電話対応が可能になります。
従業員が自宅や安全な場所から対応できることで、業務の停滞を最小限に抑えることができるでしょう。
電話代行サービスの詳しいメリットや活用方法については、「電話代行サービスのメリット7選!活用方法のポイントとデメリットを解説」にて詳しく説明しています。
6-3.緊急時の電話対応マニュアルを策定する
BCPを実効性のあるものとするためには、「緊急時の電話対応マニュアル」を整備し、従業員が戸惑うことなく対応できる体制を構築することが重要です。
■マニュアルに含めるべき内容
1. 連絡の優先順位を決める
誰を最優先で連絡すべきかを明確にします。
例:重篤な影響が出る取引先や重要顧客を優先するなど
2. 緊急時のFAQを整備する
よくある問い合わせをあらかじめ整理しておくことで、現場の混乱を防げます。
例:飲食業であれば「店舗営業の有無」、物流業であれば「配送遅延に関する問い合わせ対応」など
3. 応答スクリプトの作成
誰が対応しても同じ説明ができるよう、統一された応答例を準備しておくと安心です。
例:「現在、○○の影響により対応が遅れております。復旧の見通しは未定ですが、決まり次第ご連絡いたします。」
4. クラウドPBXや転送電話の設定
物理的なオフィスが使えない場合に備え、電話の受け手をリモート先に切り替える仕組みを構築しておきましょう。
例:オフィスの固定電話を、コールセンターやリモート勤務者のスマートフォンに転送
マニュアルの策定後は、定期的な訓練の実施と、内容の見直しを忘れずに。
時代や環境の変化に応じてアップデートを行うことで、いつ起きるかわからない非常時も対応力を発揮できます。
7.まとめ
企業を取り巻くリスクが多様化する中、BCP(事業継続計画)対策の重要性はこれまで以上に高まっています。
適切なBCPを策定し、確実に実行することで、緊急時でも事業の継続性を維持し、損害を最小限に抑えることが可能です。
本記事では、BCPの基礎知識から策定手順、さらには電話対応の重要性に至るまで、実践的な観点から解説してきました。
■BCP対策の主なポイント
・事業停止リスクの軽減(売上損失・信用低下・雇用喪失の防止につながる)
・市場競争力の強化(迅速な対応により、顧客・取引先の信頼を維持)
・法令・規制対応の強化(BCP策定が義務化されつつある業界への備えとして有効)
■BCPにおける電話対応の役割
・緊急時の情報伝達手段として不可欠(Webサイトやメールが使えない状況でも機能する)
・企業の信頼維持に貢献(的確な電話応対が混乱を防ぎ、顧客の不安を軽減)
・電話代行サービスの活用が有効(被災時にも、プロのオペレーターが対応できる)
BCPは策定するだけでは不十分であり、定期的な見直しや訓練によって実効性を高めることが不可欠です。
特に、電話代行サービスを導入することで、緊急時でも確実に顧客や取引先と連絡が取れる体制が整います。
「迅速で確実な電話対応」は事業継続のカギを握る要素のひとつです。
万が一の事態に備えて、BCPとともに実践的な電話対応体制の構築にも取り組んでいきましょう。
「ビジネスアシストの電話代行サービス」について詳しくはこちら

この記事を書いたのは
ビジネスアシスト 営業部
1999年に設立。秘書検定所持の正社員スタッフだけが応対する高品質な電話代行です。25年以上電話代行を専門で行い、電話代行の使い方をはじめ、電話代行を効率的に使う方法、電話応対のノウハウなど、電話に関することを発信しています。
カテゴリー
- 電話代行サービス (21)
- 個人事業主 (1)
- ビジネスアシスト サービス案内 (4)
- 選び方 (1)
- 電話代行 (21)
- 料金 (3)
- 評判 (1)
- 比較 (8)
- おすすめ (3)
- メリット (3)
- コールセンター (2)
- トライアル (2)
- 品質 (1)
- 導入事例 (1)
- クチコミ (2)
- 乗り換え (1)
- オンラインアシスタント (1)
- 無料お試し (1)
- アウトソーシング (2)
- コスト削減 (1)
- 紹介 (1)
- 勘定科目 (1)
- デメリット (1)
- 注意点 (1)
- 代表電話 (1)
- バレる (1)
- 業者 (1)
- クレーム電話 (1)
- Slack (1)
- Chatwork (1)
- 口コミ (1)
- BCP対策 (1)
- 事業継続計画 (1)
- 災害対策 (1)
- AI電話 (1)
- 総務部 (1)